診療科紹介
専門・認定看護師の活動
急性・重症患者看護専門看護師
2020年度、専門看護師の試験に合格しました。分野は、急性・重症患者看護です。患者・家族に起きている問題を総合的に捉えて判断する力と広い視野を持って、専門看護師の6つの役割「実践・相談・調整・倫理調整・教育・研究」を果たし、施設全体や地域の看護の質の向上に努めたいと思っています。急性・重症患者看護分野のため、クリティカルな状況にある患者さんに対し、フィジカルアセスメントを活用し、集中治療後症候群(PICS)予防、意思決定支援など、多職種と協働しながら、スタッフナースのモデルナースを目指していきたいです。
 吉森夏子
吉森夏子
皮膚排泄ケア認定看護師
当院では皮膚・排泄ケア分野は3名体制で活動しています。主な内容は褥瘡対策とストーマケアです。褥瘡対策では褥瘡対策チームだけでなく、NSTなどの多職種と連携しながら取り組んでいます。ストーマケアでは、必要に応じて入院前よりストーマ造設患者さんへの介入を開始し、退院後もストーマ外来で相談・ケア指導を行うことで受容状況やニーズに合わせた関わりを心がけています。
院内外での研修会や活動を通して、尊厳を守りその方らしく、過ごしたい場所で生活ができるように、地域との繋がりを大切により充実したケアや指導に取り組んでいきます。
 大村久美子
大村久美子 園田みずき
園田みずき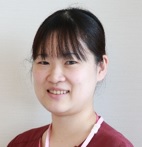 松本未来子
松本未来子
集中ケア認定看護師
平成30年度4月に福岡大学病院より異動してまいりました。
現在、集中ケアセンターHCUに勤務し、集中ケア認定看護師として、急性かつ重篤な状態にある患者に対し、フィジカルアセスメントによる病態変化の予測、医師や多職種と協働した重篤化の予防に努めています。また、家族の一員の急な入院により動揺しているご家族の不安を察し、少しでも身体的・精神的負担が軽減するよう家族支援も行っています。
院内外においてはフィジカルアセスメントや呼吸ケアなどの専門領域研修を実施し、看護師が科学的根拠に基づいた看護を提供できるよう教育活動を行っています。
私のモットーは、「患者さん、ご家族のいつもそばに」です。お元気に退院できるその日まで、そばに寄り添い、支援したいと考えています。
 林 晶
林 晶
感染管理認定看護師
感染管理認定看護師は、患者さんをはじめ、職員や医療に関わるすべての方々を感染から守ることを役割としています。院内では感染制御チーム(ICT)の一員として、部署の垣根を越えて活動するほか、地域の医療機関とも連携し、カンファレンスや相談対応を通じて、地域全体の感染対策の充実を目指しています。
自分自身、患者さん、そして一緒に働く仲間を感染から守るために、どうすればよりよい対策がとれるかを、皆さんと一緒に考え、取り組んでいきたいと思っています。
 梅原真由美
梅原真由美
救急看護認定看護師
私の使命は、地域・社会の救急医療のニーズに応え、幅広い救急看護領域の知識・技術に熟達し的確な判断に基づいた救命技術・救命看護技術の実践と危機的状況にある患者・家族への精神面に配慮した看護実践を行なうことです。病院目標の「あたたかい医療」を目指して、スタッフ指導や病棟相談を受けて急性期から患者さんの個別性に対応した援助、自己回復能力、セルフケア能力が発揮できるような質の高いケアの提供に貢献しています。
 重金勇太
重金勇太
2025年度に福岡大学病院より異動してまいりました。
救急看護認定看護師として、急変や重篤な状態にある患者さんへの迅速で的確な看護を実践するとともに、スタッフへの教育や看護の質向上に取り組んでいます。救急の現場では、一刻を争う状況の中で判断力と技術、そして冷静さが求められますが、その中でも患者さんとご家族に安心感を届けられるよう、寄り添う姿勢を大切にしています。また、救急看護の延長にある災害看護にも関心を持ち、DMATや国際緊急援助隊として熊本地震・能登半島地震・トルコ地震等での災害支援活動を行ってきました。限られた資源と混乱の中での支援活動は、平常時と異なる看護の視点と柔軟な対応力が求められ、大きな学びとなっています。今後も、救急と災害の両面から支える力や救う想いを持ち、「その人らしさ」を尊重した看護の提供に努めていきます。
 山浦章平
山浦章平
糖尿病看護認定看護師
糖尿病は障害にわたり付き合っていかなければならない病気で、患者は長い療養生活を送ることになります。そのため、患者の気持ちを大切にしながら何がよりよい方法かを、患者とともに考え、患者が療養を続けながらも自分らしい生活を送れるよう支援できたらと考えています。
 永瀬美保子
永瀬美保子
緩和ケア認定看護師
緩和ケアは、がんと診断されたときから生じる患者さんやご家族の身体やこころのつらさを和らげ、その人らしい日々を過ごせるよう支えるケアです。私は現在、緩和ケアチームの専従看護師として、多職種のチームメンバーと協力しながら活動しています。1人1人の患者さんが生きてきた人生や価値観を大切に、さまざまな苦痛を緩和し治療の方向性を自己決定したり、最期まで患者さんらしく生きられるように支援しています。教育や研修会にも力を注ぎ、いつでもどこでも誰でも切れ目なく緩和ケアが受けられることを目指したいと思っています。
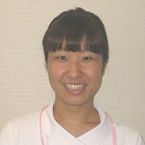 江島やよい
江島やよい
2024年度に緩和ケア認定看護師の試験に合格し、現在は内科外来で勤務しています。
私は、患者さんやご家族との対話を大切にしています。対話の中で、患者さん一人ひとりに寄り添いながら、身体や気持ちのつらさを和らげ、その人らしく生きられるようサポートしていきたいと考えています。また、将来的には院内の活動だけでなく、地域に根ざした活動にも挑戦していきたいと思っています。
 松永知代
松永知代
摂食・嚥下障害看護認定看護師
平成30年4月より福岡大学病院より異動して参りました。
摂食嚥下障害の領域は、小児から高齢者まで幅広い年代・疾患の患者さん方が対象となります。管理栄養士や言語聴覚士と協働し、年齢・疾患に関わらず全ての患者さん方が安心・安全に「口から食べる」事を目標に支援していきます。また、在宅・施設へ戻られてからも継続した関わりが出来るように、地域の医療従事者の方々と共に支援していきたいと考えています。
 緒方静子
緒方静子
摂食・嚥下障害とは、さまざまな病気や加齢などが原因で、食べ物を食べたり、飲み込んだりすることが難しくなることを言います。私は、患者さんが食べたり、飲み込んだりすることができない理由をアセスメントして、患者さんと一緒に嚥下訓練の内容や適切な食事環境を考え、安全に食べられる環境づくりに努めます。また、栄養サポートチーム(NST)のメンバーとして他職種と協働し、ひとりでも多くの患者さんが口から食べることができるように活動していきます。
 薦田千明
薦田千明
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師
脳卒中は突然発症し、意識障害や運動障害、高次脳機能障害などが生じることで患者さんやご家族の生活に大きな変化が起こります。脳卒中リハビリテーション看護の役割は、多職種と協働しながら、疾患の重篤化や合併症を防ぎ、心身の回復のために支援することです。脳卒中再発予防のための健康管理にも力を入れています。患者さんやご家族が少しでも安心して過ごすことができるよう回復期や維持期につながる看護を提供したいと考えています。
 吉田皇恵
吉田皇恵
心不全看護認定看護師
心不全はあらゆる循環器疾患の終末像であり、増悪と緩解を繰り返す慢性の予後不良の疾患です。患者さんとそのご家族は生涯心不全と付き合っていく必要があります。薬剤による疾患管理と同時に、日常生活を整える事が重要です。心不全を抱えた患者さんが、今後どう過ごしていきたいか、どう過ごせば症状を緩和させ、再入院を予防できるのか、患者さん・ご家族と共に考えています。多職種チームで協働し、心不全患者さんとそのご家族の不安が少しでも軽減し、その方らしく住み慣れた地域で過ごせるよう支援しています。
 入江未奈
入江未奈
がん薬物療法認定看護師
2024年度にがん薬物療法認定看護師の資格を取得いたしました。
がん治療のひとつである薬物療法には抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬、ホルモン療法薬など様々な薬が使用されており、使用上の注意点や副作用も複雑化しています。患者さんが安全に治療を受けることができるように、また治療によって生じる副作用の予防について知り、セルフケアを実践できるようにサポートします。患者さんの力を引き出しながら、その人らしい方法で、治療と生活を両立できるように支援したいと考えています。
 齊藤小織
齊藤小織